���ȁu����g�����Ɋւ���Q&A�v�ւ���Q�ғI�R�����g
���߂Ă̒���g����Q�ҁ��h���ҁh���s���ɑ��k����O�ɁA�u���̂��炢�͒m���Ă������v
�n�k��Ôg�̔�Q�͂���͂���ł�������ς����A��͂Ƃɂ����S�͂ł���Ȃ�̎��Ԃ��|���ĕ��������邵���������Ȃ��B�������A�����̔�Q�͉��͂Ƃ������ɂ������Ȃ����˔\�̒��x�����m�ɔF���ł����A���炩�ɂ���I������܂ł͈���ɕ����ǂ��납�������n�߂��Ȃ��ł��낤�B���͐k�В���A���S�����肳���邽�߂ł��낤���A�h�u�����ɉe���͖����v����A�����ȁA�y���ϓ����Ȃ�Ȃƌ����̂��h���m�ȏ��h�Ƃ��Ă������A���̌�A�����h�m��ʂ����h�̂悤���z��O�̔�Q���h���h���o�Ă����̂�����A�ǂ��l���Ă��h�����h�̏����u�L�ۂ݁v�ɂ���͔̂��Ƀ��o�C�B���̒��q�ł����A�Y�ꂽ���ɃL�b�g�B���ꂽ�����Ƒ傫�ȉ����̔�Q���܂��o�Ă���ᖳ���낤���Ƃ̞X�J�������Ȃ�Ȃ��B
�@�挎�i2011/06�j���Ȃ�HP���u����g�����Ɋւ���Q&A�v�Ȃ���̂��ڂ������ɋC�t�����B���e�I�ɂ͈ȉ��̂悤�ł���܂ł̔�Q�҂��܂ފW�҂ɂƂ��Ă��i�ʂ̖ڐV�����͂Ȃ��A�������X�̊��ł͂��邪�A���T�C�g�Ƃ��ẮA�����������������ƁA�كT�C�g�̂��������ɎU����Ă���h���������h�ɂ܂Ƃ߂Ă��������������Ă���悤�ȋC������̂ŁA���X�Ɍ��\�ȃT�C�g���Ǝv���Ă���B
�@�Ƃ����������̂̒���g���h���ҁh�Ή��̒S���҂ɂ܂��͖ڂ�ʂ��ė~�����C������B�������s���̒S���҂͊��Ȍ����Ƃ����"����g�����̐���"�Ȃ̂ł��邩��A���ɂ���ȏ����I�Ȏ����͏\�ɒm���Ă���͂��Ȃ̂����A���Ȃ̏�����������Ɓu���O���I�����`���b�g�������i�����ȁj�̌��������Ƃ�ǂ߂�I�v�ƌ����悤�Ȋ����ɂȂ��Ă���悤�ȋC������̂����c�B
�ƌ����̂́A�킴�킴���������T�C�g�������ɂȂ��č���邱�Ƃ��l����ƁA�����Ƃ��āA�u����g����Q�ɂ��ĉ����m��Ȃ��V������Q�ҁv�͓��X���܂���ł��낤���A����������Q�҂��܂��H�蒅���s�����A����܂��h���X�ɒP�Ȃ�S�������Ƃ��Đ��ƂƂȂ�V�l�h�Ɏ��X�ƕς���Ă���킯�ŁA�{���̐��Ƃ͂قƂ�Nj����A�����Ƃ��āA��Q�҂́A�Ȃ��Ȃ�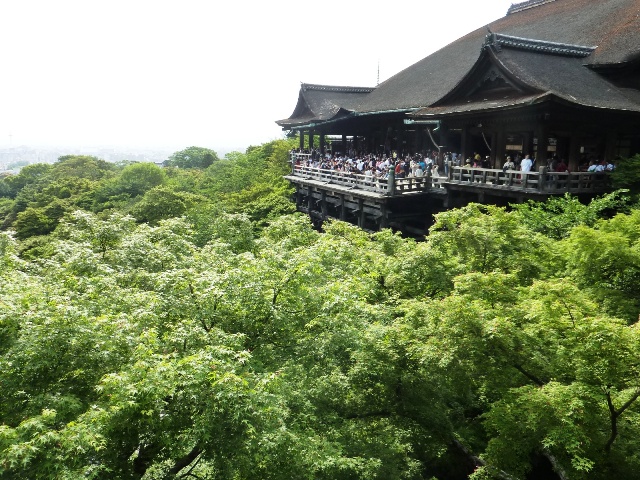
�@�������ٗl�Ɏv���C�����A����g���������ł���ƌ������Ƃ�����Ȃ�������A
�A������������ł��Ȃ�������
�B�悵��A���ꂪ�ł��Ă���̑S�̂ǂ�������ǂ��̂�����Ȃ��������
�C�ǂ����Ă��ς����Ȃ��Ȃ�܂ʼn䖝���Ă��܂����肵�āA
�@�@����Ƃ̎v����
�D�����̂֔�Q��i����܂łɎ��Ԃ��|����B
�@���̋�����ɒH�蒅�������̂̑����S���҂��A�p�ɂɂ�����ł͂Ȃ��l�ŁA�E������{�I�ɂ͐��N���o�����Ď������ւ���Ă��܂��ꍇ�����Ȃ��Ȃ��A���Ȍ����Ƃ����"����g�����̐���"�ȂLj���Ă���͂��������A�u�͂��A�҂��Ă܂����B����͂ł��ˁA�y���y���c�v�Ȃ�Ė�ɂ͍s���͂����Ȃ��̂��A���ȁh���F�h�̒���g�����Ɋւ�������̌���ł��낤�B
�ƌ������ƂŁA����g�����Ɋւ��ẮA�����������ł͒S���҂���Q�҂��g���̌��g�ƌ����ꍇ���A���ɏ����Ȏ����̂͂������A�S���҂��p�ɂɑւ��悤�Ȃ��傫�߂̎����̂ł��A���Ȃ��Ȃ��Ǝv����B�Ƃ��낪�A���ۂ́A����g���̔�Q�҂͎����̂ɒH�蒅�����ɂ͂������ɑ��\���ɉ����Ă��邢��̂����ʂȂ̂����A����S���҂́h�V�l�f�l�h�E���ł���ꍇ�����Ȃ��Ȃ��B�ŁA�l�܂�Ƃ���́A�����̑����͒���g���h���ҁh�����������Ă���̂�����Ȃ����߁A�h�N���[�}�[�h�������A�u�������ɂ͉�����܂���v�Ƃ��u����g���p�̑���킪�Ȃ��v���ƌ����āA�u��O�����v����킹��ꍇ�����Ȃ��Ȃ��ƌ����̂������ɑ����̎����̂ł̌���ƌ����悤�B
�Ƃ������ƂŁA��Q�ғI�ɂ́A���Ȃ���炻��炵���}�j���A���Ȃ���Ă��A���ۂ̌���ɉ����Ă͉�����ɂ����Ă��Ȃ��ƌ������͋����B����A���ȂƂ��Ă͉����܂Ōo���Ă�����g�����ɂ��ĉ������Ă��Ȃ��킯�ł͂Ȃ������A�s�[�����A�����Ɏ����̂ɂ́A�g�܁[�A���߂āA���̂��炢�͑��l�i���⍑�j�ɕ������Ƃ������B�ʼn��Ƃ������B�ŁA��X�������ɑ��k����Ȃ�h�Ƃ����A�s�[���Ȃ̂����m��Ȃ��A�Ǝv���킯�ł��邪�A���ۂɊ��Ȃɕ�������ǂ��������A�h�o�C�X������̂��낤�B�܂����h��O����������h�ȂǂƂ͌����Č����Ă��Ȃ����낤���Ǝv���Ȃ���c�B
���������́i�������Ƃ���́j���ҁ���Q�҂̋C��������w�������A�l�܂�Ƃ����Q�҂̒��ɂ͊��Ȃ܂ŋl�ߊ��A���Ȃ��玩���̂ւ́g��Ӊ��B�h�I�ɉ������炵�Ă����悤�ȏꍇ�������͂Ȃ��ƕ������A��{�I�ɂ͉����Ȃ��ł��낤�B�������������Ă���邩���m��Ȃ��ƌ����悤�ȓ��Ă̂Ȃ������Q�҂ɋ�����Ƃ́A���Ɩʓ|�ȂƎv�����A���͔�Q�҂����Ȃɂł����k��������@���A�������Ƃ������ɕK��������������킯�ł͂Ȃ����A��������ł��i�߂�\���̂��錻���I�ɂ́g�L���ő��h�̕��@�̂悤���B
�ƌ���������������ƌ����킯�ł�����܂����A���ȓI�ɂ������̂̒S���E���͗��Ƃ����g����g�����̐��Ɓh�ƌ����F���̂͂��ŁA���̂��߂Ɂu����16�N�x�ɍ쐬�����u����g�����Ή��̎�����v�y������g�������������邽�߂̒m�����L�߂邽�߂ɁA����16�N�x�`20�N�x��5�N�Ԃ�19�����A���אl��1844���̎�u���������v�ƌ����l���u�K�������Ȃ́h���Ɓh���u�t�Ƃ����J���Ă�����ł���A�Ⴆ�A�o�Ȃ��Ȃ������̂̒S���E���ł��g����g����菈���Ɋւ���u��b�v�́h���g�͂����ɂ܂Ƃ߂čڂ�������A������x�͌���ŏ��������h�Ƃ����悤�ȓ��e���B
�Ƃ͌����A���������t�@�C�����A�b�v���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƌ������Ƃ́A�����̃��x���̒���g����菈���͊��ȓI�ɂ͎v�킵���Ȃ��Ȃ̂�������Ȃ��B�����
�@�@�����̂̒S���҂͑��ɖZ�������Ƃ������ς������Ē���g�����ɂ��܂��Ă����ɂ͂����Ȃ��A�Ƃ����_�����낤���A
�@�A���̎�������̂������I�Ɍ���ɉ����Ă͖𗧂��Ȃ��A
�@�ƌ����悤�ȏꍇ������킯���B
�������A���R�Ȃ����������ɉ����ĕK���Ȃ͔̂�Q�҂ł���A���Ȃ��Ƃ��u�������ւ̈ӗ~�v�͎����̐E����ꡂ��ɏ���A�����̑����֕����܂łɂ͐E�����g�m�������h���Ă��邩���m��Ȃ��̂ł���B����������������̏͒���g����Q�҂ɂƂ��Ă͋ɂ߂č��ł͗L�邪�A�P�Ɏ����̂Ɂg���v��h���Ă��Ă�����͐悸�ԈႢ�Ȃ���ɐi�ނ��Ƃ͂Ȃ��ƌ������Ƃł���B
�@�Ⴆ�A�G�R�L���[�g����g��Q�ɂ���-����s�̉���������ɕt���Ă��A�g��O�����h�ɂȂ�\������ŗL��A�ƌ������ƂŁA�܂������̒��x�́g�w�K�h���Ă����A�ꉞ�A�g��O�����g�ɂȂ邱�Ƃ͏��Ȃ��ł��낤���A�h�Q�ƒl�̑�����i���ȁ@����g�����Ή��̎�������ɂ�����Q�ƒl�̎戵�ɂ��āj�g�ɂ����Ă��^�_�߂��邱�Ƃ͂Ȃ��A���̌����������̔C���ŗL�떳��ɂ�����̂ł͂Ȃ��A���Ȃ܂Ŕ�Q�҂͌l�̗͂ŏグ������悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��낤���A�ȂǂƂ����A�S�������Ď�����Ȋ��Ȋ��̖ϑz�I�Ȍ��������Ă݂��B
Q�P�@����g�����ւ̊��Ȃ̑Ή��͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��܂����H
Q�Q�@������͂Ȃ��쐬���ꂽ�̂ł����H
Q�R�@������ɂ͉��������Ă���̂ł����H
Q�S�@�w�Q�ƒl�x�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł����H
Q�T�@�w�Q�ƒl�x�����ł́A����g���������ł͂Ȃ��̂ł����H
Q�U�@�w�Q�ƒl�x�ɉȊw�I�ȍ����͂���܂����H
Q�V�@���o臒l�Ɓw�Q�ƒl�x�͈Ⴄ���̂ł����H
Q�W�@�w�Q�ƒl�x�͂������l�ł͂Ȃ��̂ł����H
Q�X�@�w�Q�ƒl�x�͕��ԁi���͔��d�j�ɂ͓K�p�ł��Ȃ��̂ł����H
Q10�@���͔��d����A����g�����o�Č��N������ɉe��������ƕ����܂������{���ł����H
Q11�@���ԂɊւ��鑛�������g���ɓK�p�ł����͂���܂����H
Q�P�@����g����Q�Q�@�����Ȃ̑Ή��͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��܂����H�@�@�@
Q�P�@����g�����ւ̊��Ȃ̑Ή��͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��܂����H
A�P�@���Ȃł́A����g�����̑Ή��̂��߁A����16�N�Ɂu����g�����Ή��̎�����v���A����14�N�y�ѕ���20�N�Ɂu����g���h�~��W�v�A�u����g���Ή�����W�v�����܂Ƃ߁A���\���܂����B
���̓��e�Ɋ�Â��A���C�����s���āA����g��������̋������s���Ă���n�������c�̓��ɑΉ������肢���Ă���܂��B
�@�܂��A��ʂ̕������̉�����Ƃ��āA�u�悭���������g���v���쐬���Ă���̂ŁA�������������B
�Ȃ��A���Ȃł́A���Ƃ��Ēʏ핷�������C�U���̂����A���g���Q�OHz�`�P�O�OHz�̒Ⴂ���g���̉��ƁA���Ƃ��Ă͒ʏ핷�����Ȃ��Q�OHz�ȉ��̋�C�U�����A�܂Ƃ߂āu����g���v�ƌĂ�ł��܂��i�Q�OHz�ȉ��̋�C�U�����w���ꍇ�́A�u������g���v�ƌĂ�ł��܂��j�B
�i�t�q�k�j
�u����g�����Ή��̎�����v
�u����g���h�~��W�v
�u����g���Ή�����W�v
�u�悭���������g���v
�@��ʂ̕������̉�����ł����u�悭���������g���v���̃R�����g
Q�Q�@������͂Ȃ��쐬���ꂽ�̂ł����H
A�Q�@�����T�N�x���������g���̋������̌X���ɂ��蕽��12�N�Ɂu����g���̑�����@�Ɋւ���}�j���A���v���쐬���܂������A����ȍ~�A����ɒ���g���̋��͋}���ɑ������܂����B�Ȃ��ł��Ñ����i���ƂȂ鑛���ȊO�̑����j���������i�������x�����Ⴂ�j�A�Â��Ȓn��̉Ɖ����ɂ�����A����������g���Ɋւ�������������܂����B���������̂悤�Ȓ���g���ɂ��đ�����@�͎����ꂽ���̂́A���ɂǂ̂悤�ɑΏ����Ă����������m�ł͂���܂���ł����B��������P���邽�߁A����16�N�Ɂu����g�����Ή��̎�����v���쐬����܂����B
�@��ʂ̕������̎��̋L���ł͂��̂�����Ȃ́u�Ñ����i���ƂȂ鑛���ȊO�̑����j���������i�������x�����Ⴂ�j�A�Â��Ȓn��̉Ɖ����ɂ�����A����������g���Ɋւ�������������܂����B�v�Ƃ��邪�A���������͑S���������Ă����悤�ȋL��������A����Ɂu�����Ȓ���g���v����Ƃ��Ă�����������h�����h���x���ɕC�G����悤�Ȣ�Q�ƒl��̂悤�Ȑ�ΓI�Ȑ��l�͏o�Ă��Ȃ������͂��ŁA�ǂ�����t�̂悤�ȋC������B
Q�R�@������ɂ͉��������Ă���̂ł����H
A�R�@������ɂ́A[1]���\�����ē��e�̔c���A[2]����̊m�F�A[3]����g���̑���A[4���肳�ꂽ����g���̕]���̕��@�A[5]��̌����A[6]����ʂ̊m�F�Ƃ�����A�̋ؓ��ɂ�����A��̓I�ȕ��@��z�������A�Z�p�I�ȉ�������荞�܂�Ă��܂��B����W�ƕ����ėp���邱�ƂŁA����g�����̉�����}�邱�Ƃ����҂���Ă��܂��B
���ɁA����g���̕]���̕��@�Ƃ��ẮA���������ő��肳������g���Ƌ��ґ��ő��肳������g���̑Ή��W�ׂ邱�Ƃ����ɏd�v�ł��邱�Ƃ��q�ׂ��A�Ή��W�ׂ���@��������Ă��܂��B����ƕ����āA������ł́w�]���w�j�x��������A����܂ł̎�@�ł͑Ή��̓�����������ȁi�������x���̒Ⴂ�j����g���Ɋւ�����ɑΉ����邽�߂ɁA�w�Q�ƒl�x����Ă���܂����B
�@�u������v�͂�����������g������S������s���̑����E�S���҂ׂ̈ɏ����ꂽ���m�ł͂��邪�A�u���\�����Ďҁi���������E��Q�ҁj�v�̂��Ȃ��Ƃ��Ă��A�s���Ƃ��Ă͂��̂��炢�͂��Ă��ꂻ�����ƌ������Ƃł���A�u���\�����Ďҁv�Ƃ��Ă͍s���̑����ɏo������O�Ɂh�G�́h�u��A�̋ؓ��v���炢�͓��ɓ���Ă������Ƃ��Œ���K�v�ł��낤�B
�@�i�P�j��Q�҂�[1]���\�����ē��e�̔c���͈ꉞ�����̍s�����u�ЂƂ܂����������͕����Ă����v�ƌ������Ƃł���B����[2]����̊m�F���炢�܂ł́A����ɗ���A���Ȃ��͕ʂƂ��ĕ����Ă����ł��낤�B
�s���ɐ\�����Ă�v�ꍇ�ɁA���Ȃ������������Ȃ܂������ɁA��X�ɒ���g�����Ƃ��đi������A�g�s���ɂƂ��čň��̏ꍇ�h��[3]����g���̑����ƌ������ɂȂ�A�ʓ|�Ȃ̂ŁA�҂��Ă܂����Ƃ�����u����g���p�̑���킪�Ȃ��v�Ƃ��u����Ȃ��v�Ƃ��u�Z�p�҂����Ȃ��v�Ƃ���������邩���m��Ȃ��B�������A��̂ɂ���Ȃ��Ƃ͂����Ă͂����Ȃ��A���Ȃ��Ƃ������x���ł͒���g����p�̑����͎����͂��ŁA���������̂��u���肢�v����Α�����\�Ȃ͂��ł��B
�@�܂�́A�P�ɂ����������Ƃ��ʓ|�Ƃ��A���Ɍ䐢�b�ɂȂ肽���Ȃ��ƌ����悤�Ȏ����̂̑Ӗ��Ɖ���Ȃ��ʎq�̂��߂ɑ���ł��Ȃ��킯�ŁA�g[2]����̊m�F�h�������炸�A�I��点���Ă��܂����Ƃ��܂��܂����Ȃ��Ȃ��A������g����g�����̎����̂ɂ���O�����g�ƌĂт܂��B
�@�i�Q�j�K������킪�L�葪��ɑ��������A�g[3]����g���̑����g�Ɏ����Ă��A���肪��ƂƂ��ł���A�܂��h�ǂ��h���A�G�R�L���[�g�A�G�l�t�@�[���Ȃǂ̉ƒ�p�@��ł�����@�h�s���̖������s����g�Ƃ��A�����̐E���̖�ԋƖ��́h�����g�Ƃ��ŁA���葤�i���������j�ł̑��������߂ł̑��肪����A�u����g���̕]���̕��@�Ƃ��ẮA���������ő��肳������g���Ƌ��ґ��ő��肳������g���̑Ή��W�ׂ����Ƃ����ɏd�v�v�Ƃ����_���S����������Ȃ��ꍇ�����Ȃ��Ȃ��B
�@�i�R�j��ނ��A[4]���肳�ꂽ����g���̕]���̕��@�ɂ����āA����g���́u�������v�̑Ή��W�͔�Q�҂̒��o�ɂ��P��on-off�i��Q�҂ɕ������邩�ǂ�������҂������j�������鎖�ɂȂ�̂��낤���A���ۏ����������x�ŐÂ��ł��邩�A������x���������傫���Ȃ��Ɩ��m��on-off�ɑΉ����邱�Ƃ͓���ł��傤�B���ۓI�ɂ��̒��x�̉�������g�����ƂȂ�̂ł���A���߂Ă����ɗ����l�ł�����悤�ł������͏��������̉\���������ł��傤�B
�@���݂Ɏ��̓G�l�t�@�[���̒�����g�����Q�҂̂�����ł��̐U�����h�����h�������Ƃ邱�Ƃ����������̂ł����A���̔ӂ���3�ӂقǁA���肪���ɐȂ�܂����B���ꂪ������g���̉e�����ǂ�����x�̑̌��ł͉���܂���̂ł܂��̋@������Ǝv���Ă��܂��B
�B
�@�����āA���ǍŏI�I�ɂ����̑���l�����ɏo�Ă��颎Q�ƒl��ɏƂ炷���ƂɂȂ�̂����A���Ȃ��̔�Q����ɋ����n�����g���͐悸�ԈႢ�Ȃ��g�u�Q�ƒl�v�ȉ��Ŗ�薳���ɂȂ�h�ł��傤�B����̍ł���ꍇ�����ԑ����ł����B������g��Q�ƒl��ɂ�����g�����̑������h�ƌ����A�Ȃ��Ȃ�[5][6]�܂ōs���Ȃ��̂����B
�@���Ȃ��̌���̑���l��Q�ƒl��ɏƂ点�A�悸�ԈႢ�Ȃ��������̒���g���̉����͑S����薳�����ƂɂȂ�ł��傤�B�i�ƌ����̂́u�Q�ƒl�v�͌��X����ł̑����l�����ɂȂ�l�Ȑ��l�ɂ͐ݒ肳��Ă��Ȃ�����ł��B�����A�z�������͊ԈႢ�Ȃ����ł��B�j�����̂̒S���҂͂����ŁA�g�ł��傤�B�����Ă����傤���Ȃ��ƍŏ����猾�����ł��傤�h�A���Ă͌���Ȃ��܂ł������悤�ȓ��e��������ł��傤�B
�@�������A�����Œ��߂Ă͐܊p���̃y�[�W��ǂ�ł�������������������܂���B�������炪�n�܂�ł��B
�@�g����g�����Ɋւ��A�@������Q�ƒl��͌����̔�Q�̋����ɂ͑S���𗧂����A��Q�̔ے�ɂ̂ݖ𗧂��l�ł������Ƃ��A���Ȃ����F������Ɠ������s���Ɋm�F�������i�ނ�͂�����ŏ�����m���Ă���̂Ŗʓ|���}���̂ł��傤���A���̖ʓ|��������j���Ƃ�����Ƃ��K�v�ł��B�����āA�����̐E���ɂ�����L�^�Ƃ��Ďc�����A�����A�Ⴆ�A�u���Ȃ̐�������Q�ƒl�ɏƂ炵�āA���Ȃ��̑�������̒���g���͑S�����L��܂���v�ƌ����悤�Ȃ��h�n�t���h�i�������j��Ƃ��K���o�����܂��傤�B�����Ȃ��Ȃ��o���Ȃ��ł��傤���疧���ɍŌ�̂�����^���ł����܂��傤�B�����āA�����������ꂪ�L�������Ƃ��s��������Ȃɓ`����悤�Ɍ����Ă����܂��傤�B
�@���������h�Ӗ��̂Ȃ����������茋�ʁh���S���I�ɐςݏグ���邱�Ƃɂ��A����g���������ɍۂ��A��Q�ƒl��ɂ���Q�̑�����͑����i�K�̎��������I�ɂ͔��ɕ֗��ł������A����g�����̐^�̉����ɂ͑S�����\�ƌ������������̗��Ƃ��Ď��m�����Ă����܂��傤�B���͂��������s���̎�Ԃ��Ȃ��u������������v�͑����̍s���Ō�����B
�@���Ȃ�D�ӓI�ɉ��߂���A�����������Ȃ����������t�@�C�����o���˂Ȃ�Ȃ��̂́A����܂Ŕ�Q�҂̎����̂ւ̔�Q�ׁ̍X�ł͂��邪���X�Ƃ����i��������A�����̑����͂��̏����ɍ���A�����Ɂh�ǂ���������́H�h�Ƃ��f�����Ă����̂ł��傤�B�c�O�Ȃ��ƂɊ��Ȃ͉��X�̔�Q�̌�����K�������\���ɔc���ł��ċ���Ƃ͎v���܂���B���������Ȃ̗v���ɑ��Ď����̂��\���ɑΉ����Ă���Ƃ��v���܂���B����͊��ȓI�Ɍ����A�����̂̒��ڑ������Ӗ��ł��邩���\�ł��邩�Ȃ̂ł��傤���A����͏��ʂ̎���ɂ��d���Ȃ����ƂȂ̂ł��傤�B��������Ӊ��B�I�Ɂu�����̒S���v������ɂ́A���Ɋ��Ȃփ��[���A�d�b����l�Ȍ`�ŁA��Q�҂̒��ڂ̐����A�����Ƃ����Ƒ����A�����Ƃ����Ɛ����ɂ��āu�����̒S��������ӂ߂�v�ƌ������Ƃ��Ǝ��͗������Ă��܂��B
�@�ƌ����̂́A�g��Q�̌������Ȃ��h�Ȃǂƚ����Ă���n���́A�������Ή��̋�J�Ƃ��A�ʓ|���𗝉����Ȃ����Ȃɏ����ƌ�������肻�̂��̂��g�グ�āh���Ȃ��\������Ȃ̂ł��B����͂Ђ��Ă����ȓI�ɂ́g��Q�̌����ɂ̂Ȃ����ĂɑΏ����悤���Ȃ��h�ƌ����G�N�X�L���[�Y�邱�Ƃł���A����͓��R�Ȃ���\�Z���t���Ȃ��ƌ������ƂŁA��̓I�Ɍ����A���ȂƂ��Ă����{��������H�w��Ɂg�����̂��d���h�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��A�ƌ������Ƃł��傤�B�ǂ�Ȏd���ł������͑����ŁA���̒�����v��ʐV�����������Ă��邱�Ƃ��L�邩��ł���B
Q�S�@�w�Q�ƒl�x�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł����H
A�S�@����ނ̂������⎺���ł̕s�����Ȃǂɂ��ċ��\�����Ă��������ꍇ�ɁA����g���ɂ����̂��ǂ����f����ڈ��ƂȂ�l�ł��B
�@������ł́A����g���̑�����s���A�܂��A�P�j���������̑��茋�ʂƋ��ґ�̑��茋�ʂ̑Ή��W�̗L�����m�F���܂��B�Ή��W���Ȃ���A���肳�ꂽ�������ȊO�������ł���\��������܂��B�Q�j�Ή��W���F�߂�ꂽ�ꍇ�ɂ́A���ґ�̑��茋�ʂ��w�Q�ƒl�x�ȂǂƏƂ炵���킹�āA���̌���������g���ł���\���ɂ��Č������܂��B
�P�j�́A��̓I�ɂ́A�ȉ��̂悤�ɍs���܂��B
1. [1]�������^�������g���̔������̎{�݁E�@�퓙���ғ��E��~�������Ƃ��ɁA���҂̋��̏ɕω������邩
2. [2]�������Ƌ��ґ�ł̑��茋�ʂ��r���āA�������x���̕ω�����g�������ɑΉ��W�����邩�ǂ���
�@�w�Q�ƒl�x�Ƃ́A�������̉ғ��Ƌ����e�ɑΉ��W������ꍇ�ɗp������̂ł��B��̓I�ɂ́A���肳�ꂽ�u������g���̒���g�����A���̒l�ȏ�ł���A���̎��g���̒���g�������̌����ł���\���������v�Ɣ��f���邽�߂́A�u���̒l�v�ł����āA���g�����ɒ�߂Ă��܂��i�P�^�R�I�N�^�[�u�o���h���S���g�����y��G�����������x���j�B
�@�Ȃ��A��ʂ̐��������ɂ�����g���͑��݂��Ă��܂����A���܂�C�ɂ͂Ȃ�܂��A�e��������܂���B����g���ɂ��āA�ǂ̒��x�̑傫���̉������x�����������Ă���̂����d�v�Ȃ̂ł��B
�u����g���ɂ��āA�ǂ̒��x�̑傫���̉������x�����������Ă���̂����d�v�Ȃ̂ł��B�v���ɂ������d�v�Ȃ̂ł����A�������Ȃ���A�c�O�Ȃ��ƂɁA��Q�ƒl��͎������œ���ꂽ�g�C�ɂȂ鉹�̑傫���h�̉������x�����l�������Ă���ɉ߂��܂����B�����A���̒l�͓s��̌����̒��ł��A�S���Â��ȏZ��n�ɉ����Ă��A�܂��A����A�����������l�ł���A���̑���ɂ�鐔�l�̑��Ⴊ�L��܂���B
�������A����́g������P���ɉȊw�I�Ɏ����ɂ͎d���̂Ȃ��h���ƂȂ̂ł��傤�B�����āA�P���ɉȊw�I�Ɏ����ɂ́g��O���̂Ă�h���Ƃ��d���̂Ȃ����Ƃł��傤�B�������A����������g������ɂ��Ă���l�����i����Q�ҁj�̑���l�����̢�Q�ƒl��ɗ]��ɂ����Ă͂܂�Ȃ��Ƃ���A����͇@���͐�̂Ă�ꂽ�g��O�I�Ȑl�����h��ΏۂƂ��ׂ��ł������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����g���̊��m�͂͌l�����傫�����͂��ꂱ���A�����̗��ŗL��Ǝ��͂������쐬�����l�����ł����m���Ă���̂ł��B��O�̕��������悤�ȋK���͋K���Ƃ��Ă̖�ڂ��ʂ����܂���B������ς�����̕��@���̂��Ԉ���Ă���̂����m��܂���B
�l�Ԃ������C�ɂ���A�C�ɂ��Ȃ��͎��ԓI�A���I�A�����āA�������l�I�ȑ̒��I�ɂ����قȂ�ł��낤���Ƃ͒N�����o���シ�邱�Ƃł��傤�B��������@���Ȃ�ꍇ�ɂ��������C�ɂȂ�Ȃ��悤�Ȑl������ł��傤���A�����������Ɂu�ُ�ɓ݊��Ȑl�v�́A���������ɉ����Đ�̂Ă�ꂽ��������̗�O�̂͂��ł����B
���ʂɌ����A�d�����̍H����i���w�҂ł͂���܂���B�����œ����Ă���l�ɂ͋��炭�����͂��܂�C�ɂȂ�Ȃ��ł��傤�B�j�Ƃ��A��s�@���Ƃ��A�n���S���Ƃ��ł͂܂��ԈႢ�Ȃ������Ƌ��ɑ����ɑ傫�Ȓ���g���������Ă��Ă���͂��ł����A����Œ���g����Q�҂ɂȂ����l�͂قƂ�ǂ��܂���i�R�b�N�s�b�g�̑��c�m������g����Q�ɑ������Ƃ�������VAD�j�B����͑��̑����̎��g���̑����ɕ���A����̎��g���̑����������ɕ\��邱�Ƃ͂Ȃ��A�����ĉ������l�Ԃ̊����������ɂȂ�e���V�������オ���Ă��邩��ł��B���ꂪ�����ƌ���������g�����h�����h�̌����A�u��ʂ̐��������ɂ�����g���͑��݂��Ă��܂����A���܂�C�ɂ͂Ȃ�܂��A�e��������܂���v�ƌ�������g���Ȃ̂ł��B�Â��ȏZ��X�ŕ��ʂɕ�炵�Ă���ꍇ�ɂ͂��������������L��܂���B
����ƁA����ɓ��낤�Ƃ��鎞��[��̑��̉����S���������Ȃ��悤�ȏZ���ł́ATV�̃{�����[���ł��������܂��B�o����^�C�}�[���Z�b�g���Ă����܂��B��������ΐ^�钆��TV�̉��̖ڊo�߃X�C�b�`���悤�Ȃ��Ƃ�����܂���B
�@�ł��A���̎������������Ȃ�����p�����鉹���������Ă��܂�����A���̉��͗Ⴆ�����ȉ��ł��C�ɂȂ�܂��B����ɁA���̉����p���I�ɒႭ�u�E�[���v�Ƃ��������炻�ꂪ����g���ł��B�Ⴆ���ꂪ�����ȁh��̖��悤�ȁh���ł��낤�ƁA����������Ԃ������Ƃ܂��܂��C�ɂȂ�܂��B���ꂪ��Ȃ�}�Y�ԈႢ�Ȃ��E�����Ɗ撣��ł��傤�B��͎E���Ή��͂��܂���B�������A����g���������͓P������܂ő����܂��B����2���u�������������v�ƌ������ƂŁh�Ȋw�I�h�ɍ���������̂�"����"�̎�ł��B�Ⴆ�A�u���Ԃ���@������g�����o���Ă���v�ƁB
�@
�@�����āA���������g����Q�҂��ꂵ�߂�͍̂���������̂́A����ɖ`�����ƁA�Ⴆ�ǂ�Ȃɏ����ȉ��ł��A���̉��͕���邱�Ƃ͂Ȃ��A�ނ����h�����I��I�h�ɂ��̌p���I�ȋ@�B���Ȃǂ�l�Ԃ̎��͒T���Ă����Ă��܂��̂ł��B���̏ꍇ�ɂ͍ő��A�u����g���ɂ��āA�ǂ̒��x�̑傫���̉������x�����������Ă���̂����d�v�v�Ȃ̂ł͂���܂���B��Q����ł̒���g���I���͂������s�q������̂ł��B���������g���ɑ���h�_���{�����ہh�Ǝ��͖��t���Ă��܂��B
������������A���̖����h�����h�B�͒���g����Q�ւ̑�Ƃ��āA�@�Ⴆ�������Ă��C�ɂ���ȇA�������Ă�����͕������Ȃ��͂��̉�������l�̑̂ɉe���͂Ȃ��ȂǂƁA�ꂵ�����X�̒����疖���I�ɑi���Ă�����Q�҂��g���_�_�h�Ő������悤�ȂǂƂ��܂��B
Q�T�@�w�Q�ƒl�x�ȉ��ł́A����g���������ł͂Ȃ��̂ł����H
A�T�@����l���ǂ̎��g���ł��w�Q�ƒl�x�ȉ��ł���A�����̏ꍇ�A����g���͌����ł͂Ȃ��ƍl������̂ŁA�P�O�OHz�ȏ�́i����g�ł͂Ȃ��j������A�n�Ղ̐U���ȂǑ��̌����ɂ��ĐT�d�Ɍ�������悤������Ŏ����Ă��܂��B���ƂȂ���g���⌴��������Ă���A�\���ȑ�̌��ʂ������Ȃ�����ł��B�������A�����Ɍl�������邱�Ƃ�����A�w�Q�ƒl�x�ȉ��ł����Ă�����g���������ł���ꍇ���ے�ł��܂���B���̏ꍇ�́A�ڂ�������������悤�A�u������v�ł͊��߂Ă��܂��B
�@�Ȃ��A���������Ƃ̑Ή����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���Ҏ��g�̖��i���蓙�j�̉\�����l�����܂��B����Ȃǂ̋��Ҏ��g�̖��̉\���ɂ��ẮA���҂̐\���o�𒍈Ӑ[�������Ȃ���A���̓��e����w�I�E�����I�ɔ��f���邱�Ƃ��K�v�ł���A�ŏI�I�ɂ͐��Ƃ̔��f���K�v�ł���Ƃ��Ă��܂��B
�@�w�ǂ́g����g�����ҁg�ɂ����āA���o�ُ̈�Ȃǂ���w�I�ɔ��f����邱�Ƃ͂���܂����B�������A����炵����������������Ȃ��悤�ȏꍇ�́A��w�I�����̉\��������܂��̂ŁA��w�I�����̉\����ׂ����߂ɂ����o�������Ă݂ĉ������B���݂ɒ��o�ُ̈�͑�̂ɉ����āu�������Ȃ��A�������ɂ����ꍇ�v�ł���A������������ꍇ�ُ͈�ł͖�������ł��B�����Č����A����g���ƌ������퐶���ɉ����Ă͕������Ȃ��Ă�����������������̂ł��B�ŁA���ǁA��t�����g���̐��Ƃ́h����h���ȂǂƂ����������I�Șb�ɂ���ւ��܂����A����͔ނ�ɂƂ��Ă����ꂭ�炢�������Ɋւ��鎨�̎����Ƃ��Ďv�����Ȃ������ł��B
�@�������A����g���͊O������̉��A����͓�������̉��ł���A�����������S���Ⴂ�܂��B����ɒ���g����Q�Ǝ��肪����I�ɈقȂ�_�́A����͉�����on-off�Ƃ͑S���W�����Ȃ��_�ł��B���������b���ꌩ�Ȋw�I�Șb�ō���������悤�Ȃ��ƂC�Ō����A���Ȃ������Ƃ���́A��������g���̉e���̗L�����ŏI�I�Ȕ��f�������悤�Ƃ������ƂƂ͈�̑S�̂ǂ����������X�Ȃ̂ł��傤���B��͂�A�@�Ⴆ�������Ă��C�ɂ���ȇA�������Ă�����͕������Ȃ��͂��̉�������l�̑̂ɉe���͂Ȃ�����C�ɂ���ȁA�ȂǂƋ��Ă݂���搶���Ȃ̂ł��傤���B
Q�U�@�w�Q�ƒl�x�ɉȊw�I�ȍ����͂���܂����H
A�U�@�w�Q�ƒl�x�͕���15�N�ɓƗ��s���@�l�Y�Ƒ����������ɂ����Ď��{�������������f�[�^����A��ʔ팱�҂�90���̐l���Q���ŋ��e�ł��郌�x���Ƃ��Đݒ肵�����̂ł��B���̒��������ł́A����g�����������������ɔ팱�҂��ɓ���āA�팱�҂̔��������邱�Ƃōs���܂����B�Ȃ��A�팱�҂́A�������̒��ŁA�������łȂ��S�g������g���ɗ����Ă���A�����鍜�����̉e���������̒��Ŏ��R�Ɋ܂܂�A�����I�ɔc������Ă���ƍl�����܂��B
�@��Q�ƒl����u��ʔ팱�҂�90���̐l���Q���ŋ��e�ł��郌�x���v�ƌ���10���̗�O����炴�链�Ȃ������l�ł��邱�Ƃ�����g����Q�Ҏn�߁A�����搶�����������������ƂȂ�܂����B�����A���̔�Q��i���Ă���̂͊��Ɉ�ʐl�������Ɍ��N�ł���l������g�����C�ɂȂ�Ȃ��l�ł͂Ȃ��A�C�ɂȂ�l�����ł�����A���ɔ팱�҂̒��o�i�K������ŁA��L�̂悤�ɔ�Q�҂͊��ɋ��炭�w�lj��̑傫���ɍS��炸�g�Q���ŋ��e�ł��Ȃ��h10���̒��Ɋ܂܂��͂�������ł��B���������A�ł��Y������l�������Ė��̗L�閳����_���邱�Ƃ́A����u�����҂������ăK���̘b������悤�ȃ��m�v�őS���Ӗ�������܂���B�������A�����ɉ����Ă͈�ʐl�Ɓh���ҁh�̊Ԃɂ́u�L�ׂȍ��ق��F�߂��Ȃ������v�����ł����A�ł���A�u����g�������Ƃ��Ȃ��l�Ǝ��ʂقNjꂵ���l�Ƃ̍��ق͂ǂ����琶���Ă���̂ł��傤�B�v���ꂪ�𖾂ł��Ȃ�����̎�������n��ꂽ�u�Q�ƒl�v�͒��o�I�ɂ͈Ӗ��͗L�邩������Ȃ����A�a���I�ɂ͖��Ӗ��Ȃ̂ł��B
�������A�h����g������"�́u����g�������e���͖��ł͂Ȃ��B���ɂ����Ă�����͕a�C�ł͂Ȃ��v�Ƃ��Ă��܂�����A����g����Q�҂Ɠy�U���Ⴂ�܂����炨�b�ɂȂ�܂���B
Q�V�@���o臒l�Ɓw�Q�ƒl�x�͈Ⴄ���̂ł����H
A�V�@���o臒l�Ƃ́A�Ȃ�炩�̂������Œ���g���������邱�Ƃ̂ł���ŏ��̉������x���ł��B����A�w�Q�ƒl�x�ɂ́A�P�j����ނ̂������Ȃǂ́u���I���́w�Q�ƒl�x�v�ƂQ�j�������A�U�����A�s�����Ȃǂ́u�S�g�ɌW����́w�Q�ƒl�x�v�̂Q��ނ�����܂��B�u���I���́w�Q�ƒl�x�v�ɂ��ẮA������������n�߂�ŏ��̉������x�����������ɂ���ċ��߂����̂ł��B�u�S�g�ɌW����́w�Q�ƒl�x�v�ɂ��ẮA�����Ԍp���������g�������ꍇ�ɁA�啔���̐l�����܂�C�ɂȂ�Ȃ��ŋ��e�ł���ő剹�����x���ł��B���̂悤�ɁA�u�S�g�ɌW����́w�Q�ƒl�x�v�Ɓu���o臒l�v�Ƃł͒�`���قȂ�܂��B�召�W�Ō����ƁA���ۂɂ́A�u�S�g�ɌW����́w�Q�ƒl�x�v�́u���o臒l�v��菭���傫�Ȓl�ƂȂ��Ă��܂��B
Q�W�@�w�Q�ƒl�x�͂������l�ł͂Ȃ��̂ł����H
A�W�@�������l�́A�u���̒l�ȉ��ɕۂ��Ƃ��]�܂����ڕW�i���Ȃ킿�ڕW�l�j�v��u�����Ă͂Ȃ�Ȃ��l�i�K���l�j�v�ƂƂ炦���܂����A�w�Q�ƒl�x�͂��̂悤�Ȃǂ���̈Ӗ��ł̊�l�ł͂���܂���B��Ő������Ă����悤�ɁA���\�����Ă��������ꍇ�ɁA����g���ɂ����̂��ǂ����f���邽�߂̖ڈ��ł��B
�@������ɂ��A�w�u���A�Z�X�����g�̊��ۑS�ڕW�l�v�A�u��Ɗ��̃K�C�h���C���v�Ƃ��č쐬�������̂ł͂Ȃ��v�x�Ɩ��L���Ă��܂��B
�@�u�w�Q�ƒl�x�ȉ��ł��邩��悢�v�u�w�Q�ƒl�x���Ă��邩����P���K�v�v�ƒP���ɔ��f����̂ł͂Ȃ��A���ۂ̉e���ɒ��ڂ��Ĕ��f���邱�Ƃ��d�v�ł��B
���Q�l�� ����g�����Ή��̎�����ɂ�����Q�ƒl�̎戵�ɂ���(�s���{�������ʒm ����20�N4��) [PDF 75KB]
�@�g�w�u���A�Z�X�����g�̊��ۑS�ڕW�l�v�A�u��Ɗ��̃K�C�h���C���v�Ƃ��č쐬�������̂ł͂Ȃ��v�x�Ɩ��L���Ă��܂��B�h�ɂ�������炸����g����Q���҂̎����̑����ł̑�����╗�Ԍ��݂̂��߂̊��A�Z�X�ɍۂ��Ĉ��p����A����ɑ��Ď����閈�Ɋ��Ȃ́g���p����ȁh�ƒ��ӊ��N�𑣂��Ȃ��̂ł��傤���B
�@�����̃A�Z�X�����g�ł͂��̎��Ɍ��y���Ă��܂��B�i120821�j
Q�X�@�w�Q�ƒl�x�͕��ԁi���͔��d�j�ɂ͓K�p�ł��Ȃ��̂ł����H
A�X�@�w�Q�ƒl�x�́A������x�̎��ԘA�����Ē���g��������Œ肳�ꂽ��������̉������x���ϓ��̏���������g����ΏۂƂ��Đݒ肵�����̂ł��B�y���Ԃ���̑����E����g���́A�����ɂ���ă��[�^�[�̉�]��o�͂��ς�邽�߉������x������g���������ω�����A�����ɂ���ĉ����g�U����������ω�����Ƃ�������������܂��z�B���̂��߁A�w�Q�ƒl�x�Ԃ̒���g���ɓK�p���邱�Ƃ͂ł��܂���B
���Q�l�� ����g�����Ή��̎�����ɂ�����Q�ƒl�̎戵�ɂ���(�s���{�������ʒm ����20�N4��) [PDF 75KB]
�@���̍��͓��ɕ��Ԍ��݂̂��߂̊��A�Z�X�ɍۂ��Ģ�Q�ƒl������p����A�S�R���ɂ����Ȃ����Ƃ�������ē������̂ł����A���̌㕗�ԑ����ɑ��Ăǂ����U���Ƃ���̂ł��傤���B���̓��������ł��B
Q10�@���͔��d����A����g�����o�Č��N������ɉe��������ƕ����܂������{���ł����H
A10�@���͔��d�̌��݂��i�ނɂ�A���͔��d�̑������ɂ��Ă̋��͑����Ă��܂��B���͔��d����́A�H���i���[�^�[�j�̕��艹�┭�d�@������̋@�B���Ȃǂ̉����������܂��B�܂��A����g�����o�Ă���ꍇ������܂��B��ʓI�ɉ��́A�������狗���������Ώ������Ȃ�i�����j�̂ŁA���Ԃ����邩��Ƃ����Ē����ɉe��������Ƃ͌���܂���B����A���Ԃ���ǂ̂悤�ȉ������g�����ǂ̂��炢�̑傫���ŏZ��ɓ͂��Ă���̂��A�ǂ̂��炢�����������Ώ\����������̂��A�n�`�╗�������ɋy�ڂ��e���͂ǂ����A�����������Ƃɂ���Ĕ������鉹�i�t����A�g���A�d���̖�Ȃǁj���傫���Ƃ��ɕ��Ԃ̑������͂ǂ̂悤�Ɋ�����̂��A�l�ւ̉e���ȂǁA�K�������܂��悭�������Ă��Ȃ����Ƃ�����܂��B���̂��߁A���Ȃł́A�����Q�Q�N�x���A���͔��d�{�݂��甭�����鑛���E����g���̎��Ԕc���A���ӏZ����ΏۂƂ����Љ�������A�팱�Ҏ����ɂ�钮��������������i�߂Ă��܂��B
�@���ɍ����s�̌��t�Ō����A���ԑ����͢�Q�ƒl�̑z��O�v�������̂ł��傤�B���炭�A�u�l�ւ̉e���ȂǁA�K�������܂��悭�������Ă��Ȃ��v�ƌ���������܂ł̒���g����Q�ɂ���30�N�ԑ����Ă���킯�ł�����A����̒����ɂ��A���Ԃ���̒���g���̉e�����������̐��N�ԂɁu�K���悭�킩�����v�ƌ����悤�Ȃ��Ƃɂ͌����ĂȂ蓾�Ȃ��ł��傤�B���̂Ȃ炻���Ȃ��Ă��܂��Ƃ���܂ŊW�҂��َE�������Ă����ӔC��N�ɖ₦�������ƌ������ƂɂȂ邩��ł��B�܁[�A���ƓI�\�Ԃł�����A�����ɂ͒N���ӔC������悤�Ȏ��͂Ȃ��̂ł��傤���B
Q11�@���ԂɊւ��鑛�������g���ɓK�p�ł����͂���܂����H
A11�@���Ȃł́A��ŏq�ׂ����������ƂɁA��̕K�v�����܂߂āA�K�ȑΉ��ɂ��Č������s�����ƂƂ��Ă��܂��B
��Q�ґ��̌��猋�_����ƁA���Ȃ������悤�Ȃ��Ƃ͂����܂Ō��O�ł���A�����������Ƃ͎����̑����I�ɂ͔��Ɏ�ԉɂ��|����ʓ|�A�o���Ȃ��̂ŁA����g�����́g��Q�ƒl��ɂ�鑫����h�ɂ��g��Q�҂̖�O�����h�A�����Ă���ƌ������Ƃł��B�]���āA��Q�ґ�������g�����ɑΏ�����ɂ͎����̂̑S���s�\���ȑΉ����A���Ȃɒ��ɑi���g��Ӊ��B�h�i�ƌ����͍̂��ƂȂ��Ă͍s���I�ɂ͌��O�Ƃ��Ắu����v�ƂȂ��Ă���l�ł���)�A���A�܂��܂��L���̂悤�ŁA���ɓ��Y�����̂��g�c�ɍs���h�I�ł��������̒��ڂ̘A���͋��ꑽ�����̂悤�ŁA�܂��܂��L���̂悤�ł��B�������A���F�A������݂ɗ��ݐs�����ꂽ�g�c�ɍs���h�̌����I�Ώ��ɑ�����]�ނ��Ǝ��̂�������������ł��邪�A���������g������킭�炢�͎�Ă��Ă������āA���肳���邭�炢�̈ӋC���݂Ŏ����̂ɑΏ�������ׂ��A�܂��́A���Ȃւ̓d�b���ɂ��܂��ɃA�^�b�N���Ă݂Ă��������B
�Ō�܂œǂ�ł���ėL�
110709,121005
HOME