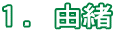 |
 本多四郎左衛門が永正(1504~20)の頃開基し、この地に草庵を創始し、実如上人から方便方身尊像の下賜を受けたのが始まりです。 本多四郎左衛門が永正(1504~20)の頃開基し、この地に草庵を創始し、実如上人から方便方身尊像の下賜を受けたのが始まりです。
寛永8(1631)年に上宮寺から順慶法師が入寺して再起したので中興開基となり、順慶から世代を一新して第一世と呼んでいます。四世租了は功労篤く、宝暦7(1757)年本堂再建、同12(1762)年土蔵を建立しました。文永元(1804)年には鐘楼堂も再建しております。
その後、寺域や諸堂宇も整えられ、六世躍恵が尾張・曽父江から入寺して寺域を拡大し、堂宇を次々と拡張再建して寺観を一新しました。文化6(1809)年現山門を、天保6(1835)年には現本堂再建を発願し、同11(1840)年落慶したとされております。本堂の正面からは見えませんが、本堂後堂の鏡板張りの天井には、迫力ある飛竜が描かれています。 |
| <豊田市教育委員会発行「豊田市の寺社建築 Ⅱ」より引用> |
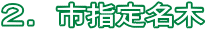 |
| 境内には大きく横に張り出した黒松(左写真:推定樹齢130年以上、枝張り130m2)と、まっすぐに伸びたすばらしい五葉松(右写真:推定樹齢100年以上、高さ14m)が指定されています
。 |
  |

