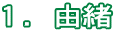 |
 寺伝によると、開基は存澄で永仁4(1296)年、本村の寺屋敷と呼ばれている地に、天台宗の一宇を構えたのが開創で、存澄は正和5(1316)年示寂(ジジャク)したという。 寺伝によると、開基は存澄で永仁4(1296)年、本村の寺屋敷と呼ばれている地に、天台宗の一宇を構えたのが開創で、存澄は正和5(1316)年示寂(ジジャク)したという。
永正元(1504)年正宗の代に真宗本願時に帰依して正宗が願主となり、野寺(安城市)の本証寺(ホンショウジ)を通じて、12月28日付で本尊を下付されており正宗は改宗開山となりました。慶長の初め(1596)頃の本証寺末に若林・教恩の名があります。
江戸時代に入って、寛文年間(1661~1673)に、無住の時代があり荒廃していたとき、渡邉家の家臣、小堀弥之右衛門が出家して宗哲と称し、入寺して再興しました。 |
 幕末から明治に及んで老朽していた堂宇を相次いで一新し、幕末には庫裡を、明治18年現本堂を起工して31年に落慶しました。以後、書院、玄関、鐘楼堂等を再建して寺観が一新されましたが、山門は大正15年の竜巻で倒壊し当時の礎石が残っているだけです。お寺には蓮如上人真筆の6文字の御書(右写真)が寺宝として保存されています。 幕末から明治に及んで老朽していた堂宇を相次いで一新し、幕末には庫裡を、明治18年現本堂を起工して31年に落慶しました。以後、書院、玄関、鐘楼堂等を再建して寺観が一新されましたが、山門は大正15年の竜巻で倒壊し当時の礎石が残っているだけです。お寺には蓮如上人真筆の6文字の御書(右写真)が寺宝として保存されています。 |
| <豊田市教育委員会発行「豊田市の寺社建築 Ⅱ」より引用> |
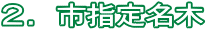 |
 昔は「お寺の大松」と呼ばれた大木が4本ありましたが、現在は1本クロマツが残っているだけです。推定樹齢は230年以上で、幹周約4m・樹高約30mと大きく真っ直ぐにそびえ立っており見事です。 昔は「お寺の大松」と呼ばれた大木が4本ありましたが、現在は1本クロマツが残っているだけです。推定樹齢は230年以上で、幹周約4m・樹高約30mと大きく真っ直ぐにそびえ立っており見事です。 |

